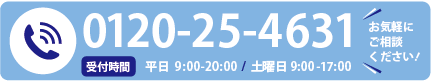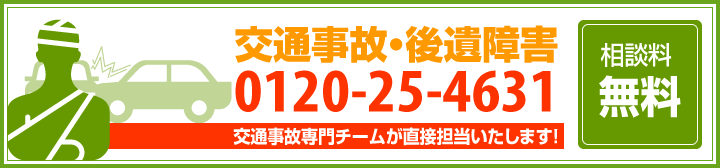交通事故に遭い、腰の痛みに悩まされている方は少なくありません。「単なる腰痛だから時間が経てば治るだろう」と考える方もいらっしゃいますが、意外と痛みが長引き、レントゲンなどに痛みの証拠が現れず、治療費が打ち切られたり、後遺障害が認められないこともあります。
このようななか、「ラセーグテスト」という検査の結果が、一つの医証として用いられるケースがしばしばあります。今回は、このラセーグテストについて、その医学的意味や重要性を詳しく解説いたします。
ラセーグテストとは何か

ラセーグテストは、腰部の神経根症状を評価するための基本的な検査方法です。患者が仰向けに寝た状態で、検査者が患者の片足をゆっくりと持ち上げていきます。この動作により、坐骨神経が伸展され、神経に圧迫や刺激がある場合は、太ももの裏からふくらはぎにかけて痛みが誘発されます。仙髄神経の中でもS1、2、3、または腰髄神経のL4、5の神経が圧迫されている状態で、ラセーグテストではその場所に負担をかけ、異常が無いかを検査していきます。
検査の判定基準
- 陽性:患者を平らな場所にあお向けにし、膝を伸ばした状態で片足を30度以上上げていきます。足を30~70度程度持ち上げた際に、腰から足にかけて放散する痛み(坐骨神経痛)が生じる場合陽性です。
- 陰性:痛みが誘発されない、または単なる筋肉の張り程度の感覚のみ。
この検査は簡便でありながら、腰椎椎間板ヘルニアや腰椎捻挫による神経根症状の有無を判断する重要な指標となります。
ラセーグ徴候とは
ラセーグテストとほぼ同義ですが、「仰臥位で膝を伸展したまま、片側の下肢を挙上させたとき、大腿後面から臀部にかけて疼痛が生じ、それ以上挙上できない状態」を言います。このような徴候を調べるのがラセーグテストということです。
交通事故とラセーグテスト陽性の関係

交通事故、特に追突事故では、車体の急激な加速・減速により腰部に強い衝撃が加わります。この衝撃により以下のような病態が生じることがあります。
主な病態
- 腰椎捻挫:腰椎周辺の靭帯や筋肉の損傷
- 椎間板ヘルニア:椎間板が突出し、神経根を圧迫
- 腰部脊柱管狭窄症の悪化:既存の狭窄が事故により症状増悪
これらの病態により坐骨神経が圧迫・刺激を受けると、ラセーグテストで陽性となる可能性が高くなります。
後遺障害認定におけるラセーグテストの重要性
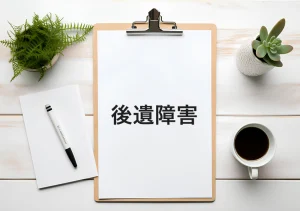
交通事故による腰部の神経症状が後遺障害として認定されるかどうかは、被害者の賠償金に影響します。ラセーグテストの結果は、後遺障害認定においてひとつの証拠となります。
ラセーグテスト陽性の場合、以下の後遺障害等級認定を視野に入れることになります。
- 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの
しかしながら、ラセーグテストは、基本的には痛みの自己申告になるので、それのみで、客観的な医学的証拠になるわけではありません。痛みのでかたが、画像所見と整合していたときに、主張を補強する材料にはなり得ます。
逆に陰性の場合、神経根症状がないと判断される材料になる可能性が高く、それを理由として後遺障害認定がされない方向にいきます。
自賠責保険は、なぜかマイナスの検査結果のみ過度に重視している気があると感じるときがあります。
ラセーグテスト以外の重要な検査

ラセーグテストは一つの検査方法ですが、これ単独で全てが決まるわけではありません。総合的な医学的評価のためには、以下の検査も欠かせません。
1. 画像診断
- MRI検査:椎間板の状態や神経圧迫の有無を詳細に確認
- X線検査:骨格の変形や不安定性の評価
2. 神経学的検査
- 深部腱反射テスト:アキレス腱反射、膝蓋腱反射の確認
- 筋力検査(MMT):下肢の筋力低下の評価
- 知覚検査:感覚異常の範囲と程度の確認
3. その他の理学的検査
- 下肢伸展挙上テスト/SLR テスト(Straight Leg Raising Test)
→背臥位で検査者が患者の脚を直線に伸ばしながら持ち上げます。痛みがある場合、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症の可能性があります。 - ブラガードテスト
→SLRテストの後、検査者が患者の脚を少し下げ、足首を曲げます。痛みがある場合、腰椎椎間板ヘルニアの可能性があります。 - FNSテスト:大腿神経の伸展テスト
→患者をうつ伏せにし、膝を曲げて太ももを後ろに持ち上げることで、大腿神経を伸張させ、太ももの前面に痛みやしびれが生じるかどうかを確認します。
これらの検査を組み合わせることで、より客観的な医学的証拠を積み重ねることが考えられます。
後遺障害認定申請時のポイント

14級9号認定のポイント
自賠責保険の基準では、14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」にあたれば認められるとされています。この中身は、以下のような基準になっています。
①「医学的に説明可能」な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの
②医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、故意に誇張された訴えではないと「医学的に推定される」もの
ここでのポイントは、①のとおり、医学的に「説明可能」かどうかです。例えば、車対車の事故でミラーを擦っただけという場合に、「衝撃があった。腰部捻挫になった。」と訴えても、医学的に見ると、その程度の衝撃でむちうちになるわけがないという事で、「医学的には説明不可能」となります。
医学的に説明可能というには、腰部捻挫や圧迫骨折等が起こるような事故態様でなければなりません。
次のポイントとしては、「医学的に証明されなくてもよい」という事です。例えば、レントゲンやMRIを取った時に、あきらかに異変が起きていれば、痛みが医学的に証明されたことになります。ただ、もともとの既往症だったり、年齢変性かもしれないという問題はあります。 画像所見がなくても、「痛みがうそではないな」と、推定できれば、14級9号が認められる可能性があります。
そのために、事故の大きさを記録して提出する(例:ドライブレコーダー)、継続的に整形外科に通院をするということが重要です(間が空くと、痛みがないと思われる)。
12級13号認定のポイント
・12級13号の認定基準は、 「局部に頑固な神経症状を残すもの 」となります。 これは、「症状が、神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により医学的に証明できる」場合に該当します。
・14級9号との認定の違いですが、14級の場合は、症状について医学的に説明可能で痛み等が推定できればよいのですが、12級の場合は、「証明」が必要となります。 したがって、症状の原因となる神経根の圧迫等が、MRI画像などで明確に見える事が最低限必要です。14級と比べて、かなり重篤な症状の場合となります。 また、圧迫やヘルニアが画像で発見されたとしても、それが、「事故により生じた」と言える必要があります。ヘルニアは、加齢により出現することもあるので(年齢変性)、医師に、画像所見をいただく際には、慎重に見ていただく必要があります。
12級獲得のためのポイントとしては、以下のものがあげられます。
①事故直後にMRIなどで精密な検査をすること
②事故の態様について証拠を提出すること
③医師が作成する後遺障害診断書の記載において、画像所見が交通事故により生じたことなどを書いていただく(因果関係)
④神経学的検査ももれなく実施する
交通事故と慰謝料について

交通事故の慰謝料には2種類があります。 ①入通院慰謝料と、②後遺障害慰謝料です。
①は、入院や通院をすることによってもらえる慰謝料です。
骨折等の重要は、むちうち等の軽傷よりは、より高額な慰謝料基準が適用されます。
- 通院期間6ヶ月の場合:基準額 約116万円
- 過失9対1の場合の請求額:116万円 × (1 – 0.1) = 約104.4万円
- 通院期間1年の場合:基準額 約154万円
- 過失9対1の場合の請求額:154万円 × (1 – 0.1) = 約138.6万円
※上記は通院のみの場合の目安です。入院期間があればさらに増額されます。
●表の見方
・入院のみの方は、「入院」欄の月に対応する金額(単位:万円)となります。
・通院のみの方は、「通院」欄の月に対応する金額となります。
・両方に該当する方は、「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額となります。
弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
弁護士費用特約で、自己負担一切なしのケースもあります。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。
骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。
なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。
※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。
弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。
過失があっても使えます。
弁護士費用特約は、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。
ご相談 ご質問

大きなケガの事故では、相手保険会社の提示額が、弁護士基準よりも大幅に低い「任意保険基準」で計算されているケースが少なくありません。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、重傷事故や死亡事故に特に注力しています。ご依頼から相談まで、すべて専門チームの弁護士が担当します(*最近、弁護士事務所によっては、面談のみ弁護士が行い、事件の進行はスタッフが主に対応する事務所もあります。当事務所はすべて弁護士が行います)。
交通事故、重傷事故でお悩みの方に適切なアドバイスができるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。