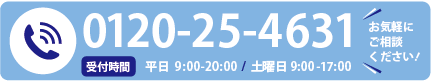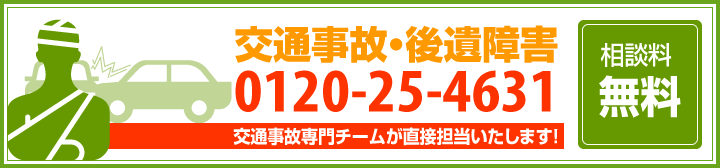紛争の内容
ご依頼者の方が、横断歩道を歩行中に自動車にはねられ、重傷を負い、後遺障害等級の認定を受けた事案です。
相手方保険会社は、被害者が高齢で無職であり、かつ同居の家族もいないことから、家事従事者としての逸失利益も認めず、後遺障害逸失利益をゼロと主張しました。
これに対して、後遺障害を負ったことによる生活上の制限を考慮し、労働能力の喪失に対する賠償として、同年齢の平均賃金を基礎とする逸失利益を認めるよう主張した点が主な争点となりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当初、相手方保険会社は、高齢・無職・単身という属性を理由に後遺障害逸失利益を全面的に否認しました。
これに対し、労働能力および生活能力の喪失は賃金センサス等に基づく平均賃金を基礎として評価されるべきであると強く交渉を継続いたしました。
交渉の結果、保険会社から譲歩案として、同年齢の平均賃金の半額であれば逸失利益を認めるという主張がなされました。
この譲歩は当初の主張(ゼロ回答)から大きく前進するものでしたが、被った損害を十分に慰謝するには至らないと判断し、あくまで全額(平均賃金ベース)を基礎とした逸失利益の支払いを粘り強く求めました。
本事例の結末
最終的に、交渉を継続した結果、相手方保険会社は、同年齢の平均賃金を基礎とした後遺障害逸失利益の全額を支払うことで合意に至りました。
これにより、被害者の方は後遺障害による将来の生活制限に対し、適正な賠償を受けることができました。
本事例に学ぶこと
相手方保険会社からの提示があった際には、しっかりと内容を検討して適正な賠償額を追求する重要でごす。
具体的には、高齢や無職といった属性は、必ずしも労働能力や生活能力の喪失による逸失利益の否定理由とはならないということに基づいて、しっかりとした主張をすることが重要です。
また、後遺障害逸失利益の算定において、労働能力の喪失は、就労状況にかかわらず、平均賃金等の客観的な指標を基礎とすることがあり得ることを主張して、それを論理的に提示することが重要です。
このように法的な理屈に基づいて交渉を続けることで、本件のように家事従事者にも該当しない単身高齢者のケースであっても、後遺障害が将来の生活に及ぼす制限を具体的に立証することで、平均賃金ベースの逸失利益を認めてもらうことがあり得ます。
交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士 赤木 誠治
弁護士 遠藤 吏恭