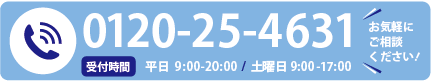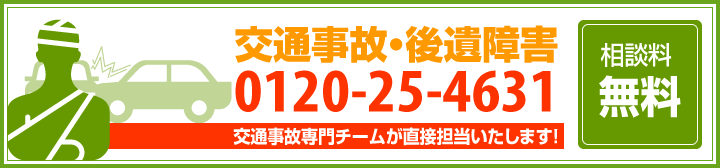交通事故に遭われた方の中には、「まさか自分が事故に遭うなんて」「最初は車の修理だけで済むと思っていたのに、後から体に痛みが出てきた…」という経験をされた方もいらっしゃるかもしれません。
もし、事故直後には何ともなかったはずなのに、数日経ってから首や腰に痛みが出たり、しびれを感じたりするようになった場合、それは決して珍しいことではありません。しかし、事故が「物損事故」として処理されたままだと、後から発生した怪我の治療費や、本来受け取れるはずの慰謝料が補償されないという不安がおありでしょうか。
後から物損事故を「人身事故」へ切り替えるという手続きは可能です。本記事では、交通事故チームの弁護士が、物損事故と人身事故の違いから、切り替え方法、メリット・デメリットを解説します。
1. 「物損事故」と「人身事故」の違いとは?

まず、ご自身の事故が「物損事故」と「人身事故」のどちらに当たるのか、その違いを正確に理解することが重要です。
- 物損事故とは?
- 車両や建物、電柱、ガードレールなど、“物”に対する損害のみが発生し、人の死傷を伴わない事故です。
- 警察が作成するのは「物件事故報告書」と呼ばれる書類です。
- 損害賠償の対象は、車の修理費、代車費用、買い替え費用、評価損など、物的損害のみに限られます。
- 人身事故とは?
- 人の怪我や死亡を伴う事故を指します。
- 警察は現場の詳細な調査を行い、「実況見分調書」を作成します。この調書は、事故状況を客観的に証明する重要な証拠となります。
- 人身事故の場合、加害者には「過失運転致死傷罪」などの刑事罰や、免許停止・取消といった行政処分が科される可能性が生じます。
- 損害賠償の対象は、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、将来の逸失利益(事故による後遺症で失われた将来の収入)など、人的損害に加えて物的損害も含まれます。
2. 人身事故だが警察には物損事故で申請している場合

体に痛みがあるにもかかわらず物損事故のままで警察に届ける場合があります。
背景には様々な理由があり、例えば、刑事罰になると困るから物損事故にしてくれと相手に頼まれたとか、大したケガではないということが考えられます。
ここで注意が必要なのが、実際にケガをしていたかどうかと、警察でどう扱うかは必ずしもリンクしないのです。
警察は、物損事故扱いにしたがる傾向にあります。警察が事故を物損事故にしたがるのは、警察が行う事故後の処理の手間が省けるという理由があるからです。
人身事故の場合、前述のように、当事者立ち会いのもとで実況見分を行い、その内容を実況見分調書にまとめなければなりません。また、当事者を取り調べて、供述調書も作成する必要があります。
他方で、物損事故では実況見分はされず、実況見分調書も作成されません。簡易な図面のみを示した「物件事故報告書」が作成される程度です。
もし警察に物損事故としての取扱いを進められても、実際にケガをしているのであれば、診断書を提出し、人身事故として申請をすることは可能です。
3. 人身事故に切替えるメリットは

まず、人身事故への切り替えをしなくても、事故による怪我に対する治療自体は可能です。
「物件事故」と「人身事故」の切り替えはあくまで、警察の事故類型分類であり、制度上の話です。そのため、実際にケガをして人身損害が発生していれば、警察で「物件事故」の扱いのままでも、加害者側の保険会社に治療費などの人身損害を請求すること自体はできます。
それなので、事故にはよりますが、「物損事故に切替えなくても」賠償に影響がない方もたくさんいらっしゃいますし、経験上もたくさんのご依頼者様が、物損事故扱いのまま示談に至っています。
しかし、人身事故に切り替えることには、被害者の方にとってメリットとなるケースもあります。
メリット1:過失割合を詳細に検討できる(実況見分調書作成の重要性)
先ほど触れましたが、警察で物件事故として処理された場合は、「物件事故報告書」という書類しか作られません。内容は簡易的であり、ほとんど参考にはなりません。弁護士が開示の請求をした場合、図の部分が黒塗りになる場合もあり、過失のある事案では、物足りない資料です。
他方で、人身事故に切り替えると、警察は加害者に対する「過失運転致死傷罪」などの刑事捜査を進める必要が生じるので、実況見分をしなければなりません。そうすると、実況見分調書や供述調書が作成され、後日、過失が争いになった場合に、資料として参考になります。
メリット2:後遺障害の場面
自賠責保険に、後遺障害の申請をするケースがあります。この自賠責保険に対する請求自体は、「物件事故」扱いでも可能ではあります。
しかし、物件事故のまま請求すると、通常提出する「交通事故証明書(人身事故扱い)」の代わりに「人身事故証明書入手不能理由書」という追加の書類を提出する必要が生じます。
これは、なぜケガをしているのに人身事故でないのかについて、つまり、警察が人身事故として処理しなかった理由や、なぜ被害者が人身事故に切り替えなかったのかについて記載をする必要があります。
実態はわかりませんが、人身事故証明書がないために、「この事故は軽微なものだった」、「ケガは軽い」と思われる可能性は廃除できません。
きちんと人身事故に切替えることで、こうした推認を廃除できる可能性はあります。
4.切り替えに伴うデメリット・注意点

人身事故への切り替えは被害者にとっていくつかのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを理解した上で、慎重に判断し、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。
- 加害者の処罰リスクが高まる
- 人身事故となると、加害者は「過失運転致死傷罪」などの刑事罰に問われたり、免許の点数制度に基づく行政処分(免許停止・取消等)の対象となったりする可能性が高まります。
- 実況見分など警察対応が発生
- 人身事故に切り替わると、警察による詳細な現場検証(実況見分)が再度行われることがあります。被害者も再度事情聴取に応じる必要があり、時間や精神的な負担が生じる可能性があります。
- 加害者からの感情的反発
- 加害者が自身の処分を恐れ、「切り替えをしないでほしい」と被害者に直接懇願してきたり、感情的な反発をしてきたりするケースがあります。
※なお、加害者からの懇願があったとしても、加害者の処分は、警察や検察、行政が判断するものであり、加害者の言動に惑わされず、ご自身の利益を優先に考えることは重要です。
5. 切り替えの具体的な手続き

では、実際に物損事故から人身事故に切り替えるにはどうすれば良いのでしょうか。主な手順は以下の通りです。
- 病院での診察・診断書の取得
- 体の痛みを感じたら、すぐに整形外科などの病院を受診してください。医師に「交通事故による怪我であること」「具体的な傷病名(例:むちうち、骨折など)と全治までの期間」を明記した診断書を作成してもらいましょう。
- 事故から時間が経てば経つほど、事故と怪我の因果関係を証明することが難しくなります。痛みや違和感を感じた際は、できる限り早期(遅くとも1週間以内が目安)に受診することが非常に重要です。
- 警察署へ診断書を提出
- 作成してもらった診断書を、事故を管轄する警察署(または事故を担当した警察官)に提出し、物損事故扱いから人身事故扱いへの切り替えを申し出てください。
- 警察による確認・実況見分
- 警察は提出された診断書と事故状況を照らし合わせ、人身事故として扱うべきか判断します。その際、必要に応じて再度、現場で実況見分が行われたり、当時の状況について改めて説明を求められたりすることがあります。
- 交通事故証明書の取得
- 警察が人身事故として処理することを決定すると、自動車安全運転センターが発行する「交通事故証明書」の内容が「物件事故」から「人身事故」へと切り替わります(または新たに人身事故用が発行されます)。この証明書は、今後の保険会社との交渉で必須となる書類です。
- 保険会社へ連絡
- 加害者側の任意保険会社、そしてご自身の任意保険会社(ご自身の人身傷害保険などを利用する場合)に対し、人身事故への切り替えが完了した旨を連絡しましょう。
6. よくある質問(FAQ)

相談者の方からよくいただく質問とその回答をまとめました。
Q. 事故から日数が経っていても切り替えできますか?
A. 原則として可能です。手続き可能な期間について「事故後〇日以内」などと明確な規定が法律で定められているわけではありません。しかし、事故から時間が経てば経つほど、警察が事故と怪我の因果関係を疑い、渋ることはありえます。捜査も難しくなってきます。
それなので、できる限り早期の対応が重要です。数週間以上経過している場合でも、状況によっては切り替えが可能な場合もあります。
Q. 診断書がなくても切り替え可能ですか?
A. 不可です。警察は医師の客観的な診断をもって、人の死傷があったと判断するため、必ず医師の診断書が必要となります。
Q. 加害者が反対している場合は?
A. 加害者の同意は、人身事故への切り替えの必須条件ではありません。重要なのは、実際に被害者の身体に損害が生じているかどうかです。
ご相談 ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
交通事故の初動対応は、その後の補償に大きく影響します。「物損で済ませたが、後から痛みが出てきた」「人身事故に切り替えたいが、手続きが不安」「加害者や保険会社とのやり取りに困っている」という方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。