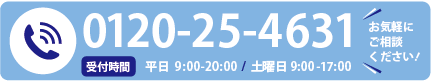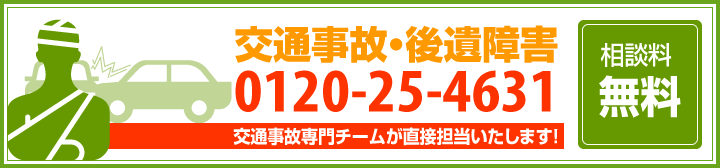交通事故によって骨折という重大なケガを負った場合、治療が終わっても痛みや可動域の制限、しびれなどの後遺症が残ることは珍しくありません。
こうした後遺症が一定の基準を満たすと、「後遺障害等級」が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償を受けられる可能性があります。
しかし、後遺障害等級の認定基準は複雑で、保険会社の提示額は必ずしも適正とは限りません。
正しい知識と適切な準備がなければ、本来受け取れるはずの金額より大幅に低い示談金で終わってしまうリスクがあります。
本記事では、交通事故で骨折した被害者やその家族が知っておくべき「後遺障害の種類・等級・慰謝料相場・認定ポイント」を、交通事故チームの弁護士が解説します。
交通事故による骨折で後遺障害が認定されるケース

交通事故での骨折は、骨の損傷部位や治療経過によって、その後の生活にさまざまな支障をきたします。
後遺障害の認定は、自賠責保険の「後遺障害等級表」に基づき、症状や障害の程度に応じて1級から14級までの等級が認められる可能性があります。
骨折の後遺障害の種類には以下のようなものがあります。
・機能障害(関節可動域の制限)
・神経障害(痛み・しびれ等)
・運動障害(脊柱の動きの制限等)
・変形障害(骨の変形や偽関節等)
・短縮障害(下肢の長さが短くなる等)
以下、それぞれについて見ていきます。
機能障害(関節の可動域制限)
交通事故の骨折で最も多い後遺障害が「機能障害」です。
関節を動かせる範囲(可動域)が制限されると、後遺障害等級が認定される可能性があります。
- 手指の場合:4級6号〜14級7号まで幅広く、症状の重さや部位によって変動します。
| 症状 | 等級 |
| 両手の手指の全部の用廃 | 4級6号 |
| 1手の手指5本の用廃 1手の手指の親指を含む4本の手指の用廃 | 7級7号 |
| 1手の親指を含む3本の手指の用廃 1手の親指以外の4本の手指の用廃 | 8級4号 |
| 1手の親指を含む2本の手指の用廃 1手の親指以外の3本の手指の用廃 | 9級13号 |
| 1手の親指の用廃 1手の親指以外の2本の手指の用廃 | 10級7号 |
| 1手の人差指、中指又は薬指の用廃 | 12級10号 |
| 1手の小指の用廃 | 13級6号 |
| 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができないもの | 14級7号 |
・手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
・中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの
・親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの
・手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの
- 上下肢の場合
上肢に可動域制限が残った場合の後遺障害等級は以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
| 1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢に可動域制限が残った場合の後遺障害等級は以下の通りです。
下肢とは、股関節・ひざ関節・足関節までの3大関節及び足指の部分をいいます。
| 等級 | 認定基準 |
| 1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
神経障害(慢性的な痛みやしびれ)

- 骨折の治癒後も神経損傷が残り、痛みやしびれなどの神経症状が継続する状態です。
認定等級の目安: - 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの。画像上痛みの原因を説明できなくても、交通事故の態様や治療経過、症状の一貫性などから医学的に説明できる場合に認定されます。特に、関節内や関節に近い部位の骨折、または癒合が不完全であることが画像上明らかな場合に認められやすい傾向があります。
- 14級9号:局部に神経症状を残すもの。骨折の態様(ひびや骨挫傷では認められにくい)、通院回数、リハビリ内容などが考慮されます。
- ポイント:単に「痛い」「しびれる」だけでなく、いつから、どのように、どのあたりが痛む(しびれる)のかなど、具体的な自覚症状を医師に細かく伝えることが重要です。
運動障害(背骨(脊柱)の骨折)、変形障害
交通事故では事故の衝撃によって背骨部分を痛めてしまうことがあります。脊柱の圧迫骨折や破裂骨折は、骨粗鬆症の高齢者ではよく見かける骨折ですが、交通事故のような高エネルギー外傷で受傷するケースもあります。特に脊柱が圧迫骨折するとやっかいです。変形障害も起こることがあります。
主な頚椎の骨折として、下記のようなものがあります。
環椎破裂骨折(ジェファーソン骨折)
軸椎歯突起骨折
軸椎関節突起間骨折(ハングマン骨折)
頚椎椎体骨折(圧迫骨折も含む)
以下のような後遺障害の可能性があります。
■6級5号:脊柱に著しい変形を残すもの
2個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっているもの。つまり、椎体1個以上の椎体前方高の減少したものです。
■8級2号:脊柱に中程度の変形を残すもの
1個以上の椎体の前方椎体高の高さの合計が、後方椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているものです。言い換えると、椎体の1/2以上の椎体前方高の減少したものであります。
■11級7号:脊柱に変形を残すもの
下記3つのいずれかに該当すれば後遺障害として認定されます。
・脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・脊椎固定術が行われたもの
・3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの
後遺障害慰謝料の基準と相場

後遺障害慰謝料は、認定等級と算定基準によって大きく異なります。
特に「交通事故 骨折 後遺障害 慰謝料」等を検索して、当記事をお読みになる方が多いようですが、この部分をご覧ください。
後遺障害が認定されると、後遺障害等級によって、「後遺障害慰謝料」を請求できます。後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
保険会社は、大抵は、【自賠責基準】に近い金額で慰謝料額を提示してきますが、弁護士が入ることにより、正当な金額で交渉が可能です。正当な金額は、以下の表のとおりです。
| 後遺障害等級 | 裁判基準 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 2,800万円 | 100/100 |
| 第2級 | 2,370万円 | 100/100 |
| 第3級 | 1,990万円 | 100/100 |
| 第4級 | 1,670万円 | 92/100 |
| 第5級 | 1,400万円 | 79/100 |
| 第6級 | 1,180万円 | 67/100 |
| 第7級 | 1,000万円 | 56/100 |
| 第8級 | 830万円 | 45/100 |
| 第9級 | 690万円 | 35/100 |
| 第10級 | 550万円 | 27/100 |
| 第11級 | 420万円 | 20/100 |
| 第12級 | 290万円 | 14/100 |
| 第13級 | 180万円 | 9/100 |
| 第14級 | 110万円 | 5/100 |
例えば、表の通り、12級に該当した場合は、290万円が正しい相場です。
1級だと2800万円にもなります。等級が高い方が慰謝料額が増加します。
保険会社の提示額は多くの場合、自賠責や任意基準で計算されており、弁護士交渉により数百万円単位で増額するケースも珍しくありません。
適正な後遺障害等級を受けるための3つのポイント

- 事故直後からの一貫した通院
診断・治療の記録は後遺障害認定の根拠となります。空白期間があると因果関係を疑われます。 - 医師への具体的な症状説明
「痛い」だけでなく、「どこが・いつから・どのように痛むのか」を具体的に伝えましょう。 - 後遺障害診断書の精査
記載不備や重要所見の漏れがないかを確認し、不十分なら修正依頼を行います。
特に、後遺障害の申請は、保険会社に任せるのではなく、被害者請求(自分で申請する)を選ぶことで、書類内容を自分で確認・補足でき、適正等級を得られる可能性が高まります。
弁護士に依頼すると、この被害者請求からサポートを受けることが可能です。
交通事故による大腿骨骨折について弁護士に依頼するメリット

後遺障害が残ると保険金額が大きくなるので保険会社と争いになることがほとんどです。
特に、慰謝料や逸失利益は金額が大きくなります。
弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万~事案によって数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所でありました)。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用も特約ででますので、まずは相談ください。
ラインでの相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。
弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
弁護士費用特約で、自己負担一切なしのケースもあります。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内でおさまります。
骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。
なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。
※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。
弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。
弁護士費用特約は、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。
【無料ライン(LINE)相談・予約実施中】
弁護士に直接、ラインで無料相談(5往復程度)できます。予約もラインからできます。
(3つの登録方法)
●以下のボタンから友達追加してトークできます
●QRコード読み取りで友達追加できます

●ID検索の場合はIDを検索して友達追加をしてください
LINE ID:【@ggu7197l】(最後の文字は小文字のエル)
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。