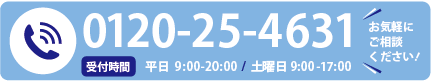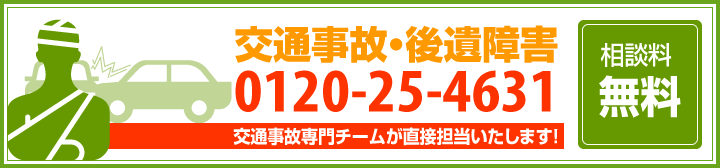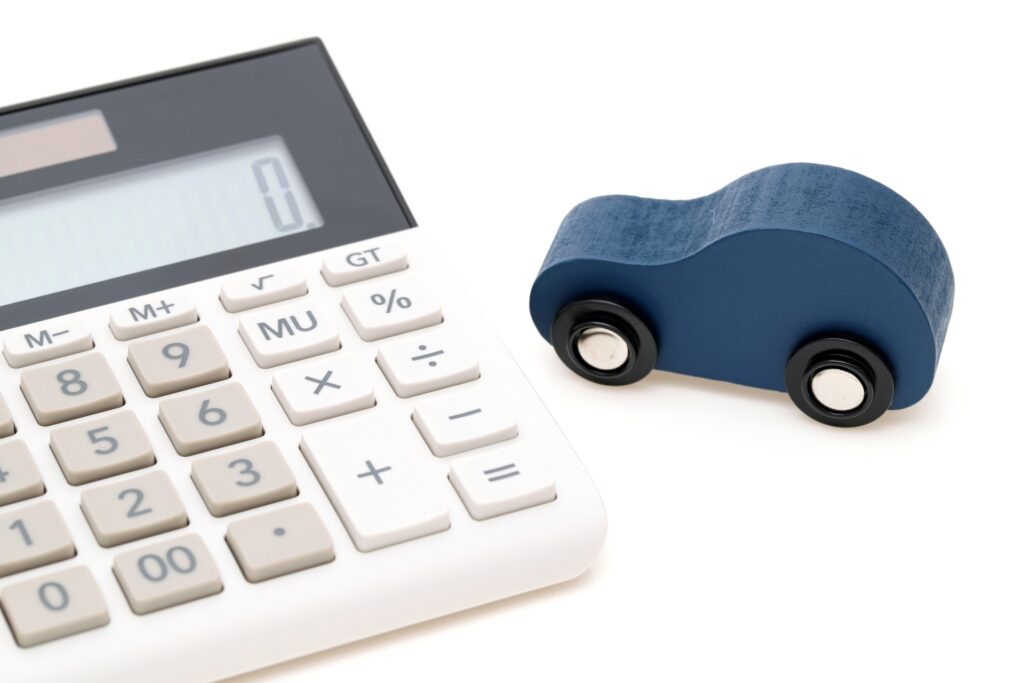
「時価額」に納得できない被害者が続出している理由

交通事故で車が大破したり、修理費が高額になったりした場合、保険会社から「時価額での補償になります」と言われることがあります。しかし、提示された時価額を見て、多くの被害者が「こんなに安いの?」「納得できない!」と感じています。
なぜこのような問題が起きるのでしょうか。そして、時価額に納得できない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。本記事では、交通事故における時価額の問題について、弁護士の視点から詳しく解説します。
そもそも「時価額」とは何か
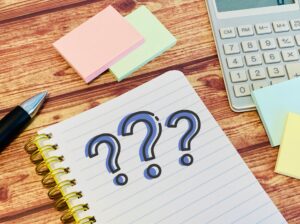
時価額の法的な定義
時価額とは、事故当時の車両の客観的な市場価値のことです。具体的には、同じ車種・年式・型式・走行距離・使用状態の車両を中古車市場で取得するために必要な価格を指します。
重要な判例として、最高裁判所昭和49年4月15日判決は、「減価償却による定率法または定額法によることは、加害者及び被害者がこれに異議がない等の特段の事情のない限り、許されない」と述べています。つまり、単純な帳簿上の価値ではなく、実際の市場価値で評価すべきだということです。
どんな場合に時価額での補償になるのか
時価額での補償となるのは、主に以下の2つのケースです:
1. 物理的全損
車両が激しく破損し、構造的に修理が不可能な状態。フレームが大きく歪んでメーカーや専門業者でも修復できない場合などが該当します。
2. 経済的全損
物理的には修理可能でも、修理費用が事故当時の時価額を上回る場合。実務では、修理見積額+買替諸費用の合計が時価額を超える場合、経済的全損と認定されます。
つまり、「修理するより買い替えた方が安い」という状況では、時価額までしか補償されないのです。
なぜ時価額に納得できないのか – よくある不満

1. 提示額が予想より大幅に低い
「10年前に200万円で買った車なのに、時価額は30万円と言われた」 「まだまだ乗れる車なのに、こんな金額では同じレベルの車が買えない」
このような不満は非常に多く聞かれます。特に、大切に乗ってきた車や、思い入れのある車の場合、感情的にも納得しづらいものです。
2. 保険会社の査定方法が不透明
保険会社が提示する時価額について、「どうやってこの金額を算出したのか」が明確に説明されないケースがあります。根拠が不明確なまま低い金額を提示されれば、納得できないのは当然です。
3. 実際に同じ車を探すと高い
中古車サイトで同じ車種を検索すると、保険会社が提示した時価額よりはるかに高い価格で販売されていることがあります。「この金額では同じ車が買えない」という現実的な問題が生じます。
4. 買替諸費用が十分に考慮されていない
車両本体の時価額だけでなく、車を買い替えるには様々な費用がかかります。これらが十分に考慮されていないと、実質的な負担が大きくなってしまいます。
時価額はどのように算定されるのか

実務で用いられる評価指標
時価額の算定には、以下のような資料が用いられます:
1. レッドブック(自動車価格月報、オートガイド社)
業者間取引の相場を反映した価格表。保険会社がよく参照します。
2. イエローブック(中古車価格ガイドブック、日本自動車査定協会)
中古車査定の基準となる価格表。
3. オークション相場
業者間オークションでの実際の取引価格。
4. インターネット上の中古車販売価格
実務でも、インターネット検索により中古車販売情報を参照することが多くなっています。
5. 専門業者の鑑定書・評価報告書
中古車査定士などの専門家による評価。
個別補正の重要性
重要なのは、これらの指標を機械的に適用するのではなく、事故直前の車両の実際の使用状況を考慮して個別に補正する必要があるということです:
- 年式・走行距離
- 整備状態(定期点検の実施状況など)
- 外装・内装の状態
- カスタマイズやオプション装備の有無
- 事故歴・修復歴の有無
保険会社が提示する時価額が、これらの個別事情を適切に反映していない場合、不当に低い評価となっている可能性があります。
時価額に納得できない場合の対応方法

1. まずは根拠を確認する
保険会社に対して、時価額の算定根拠を明確に説明するよう求めましょう。具体的には:
- どの資料(レッドブック、オークション相場など)を参照したのか
- 車両の状態をどのように評価したのか
- 個別補正を行ったのか、その内容は何か
2. 反証資料を収集する
時価額が不当に低いことを示すため、以下のような資料を収集します:
中古車販売サイトの情報
- 同じ車種・年式・走行距離の車両が、どのくらいの価格で販売されているか
- 複数のサイト(カーセンサー、グーネット、ヤフオクなど)から情報を集める
- スクリーンショットや印刷物として保存する
ディーラーや中古車販売店の見積もり
- 同等の車両を購入する場合の実際の見積もりを取得
- 複数の業者から見積もりを取ると説得力が増す
専門家の評価書
- 日本自動車査定協会などの専門機関に鑑定を依頼
- 費用はかかりますが、客観的な評価として証拠となる場合あり
3. 買替諸費用もしっかり主張する
車両本体の時価額だけでなく、買替えに必要な以下の費用も損害として認められます:
- 廃車手続費用
- 登録関連費用
- 納車関連費用
- 車庫証明費用
- レッカー費用
これらを合計すると、数十万円になることもあります。保険会社がこれらを十分に考慮していない場合は、改めて請求しましょう。
なお、自動車税や自賠責保険料の未経過分は、還付制度があるため原則として損害に含まれませんが、還付されない場合は損害となりえます。
注意点としては、「買換える予定」ではダメで、実際に買換える必要があります。
4. 保険会社との交渉
収集した資料をもとに、保険会社と交渉します。具体的には:
- 中古車販売価格のデータを示し、提示された時価額が市場実態と乖離していることを主張
- 車両の良好な整備状態や特別な装備を説明
- 買替諸費用の明細を提示
ただし、保険会社は当初の評価を簡単には変えない傾向があります。交渉が難航する場合は、専門家への相談を検討すべきです。
弁護士に相談するメリット

時価額の問題で保険会社との交渉が難航している場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。
1. 適正な時価額の算定
弁護士は、上記の方法で適正な時価額がどの程度かを判断します。
2. 効果的な証拠収集
どのような資料を集めれば説得力があるか、専門的なアドバイスを受けられます。また、必要に応じて専門家の鑑定書を取得する手配もサポートします。
3. 交渉力の向上
弁護士が代理人として交渉することで、保険会社も真摯に対応せざるを得なくなります。法的根拠に基づいた主張により、増額を引き出せる可能性が高まります。
4. 訴訟への対応
交渉で解決しない場合、訴訟を提起することになります。訴訟では、裁判所が客観的な立場から時価額を判断します。弁護士に依頼すれば、訴訟手続きを一任できます。
5. 物損以外の損害も併せて請求
交通事故では、車両の損害だけでなく、怪我による治療費・慰謝料・休業損害なども発生することがあります。弁護士に依頼すれば、これらすべてを適切に請求できます。
実際に、弁護士に依頼するのとしないのでは、数十万円から事案によっては数千万円の違いが出る可能性があります(当事務所でも実際にありました)。
6. 弁護士特約の活用
多くの自動車保険には「弁護士特約」が付帯しています。この特約を使えば、原則として300万円まで弁護士費用が保険でカバーされます。
弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用も特約で賄われますので、まずは相談してみることをお勧めします。
実際の裁判例から見る時価額の判断

裁判所は、時価額をどのように判断しているのでしょうか。いくつかの事例を見てみましょう。
事例1:中古車市場価格を重視した例
ある裁判例では、保険会社が提示したレッドブック上の価格ではなく、実際の中古車販売価格を参考に時価額が認定されました。インターネット上の複数の販売事例から、同等車両の平均価格を算出し、それを時価額としたのです。
事例2:個別事情を考慮した例
別の裁判例では、定期点検を欠かさず行い、丁寧に使用されていた車両について、通常の査定額よりも高い時価額が認められました。整備記録簿や点検証明書が有力な証拠となりました。状態が良かったという点も重要です。
事例3:買替諸費用を広く認めた例
車両本体の時価額だけでなく、登録費用、納車費用、廃車費用など、買替えに実際に必要となった諸費用を幅広く損害として認めた裁判例もあります。
これらの裁判例から分かるのは、時価額は画一的に決まるものではなく、個別の事情や実際の市場価格を考慮して柔軟に判断されるということです。
修理か買替えか – 全損でない場合の選択

修理費が時価額を超えていない場合でも、「修理するか、買い替えるか」という選択に悩むことがあります。
修理する場合
修理が可能な場合、修理していなくとも、修理費相当額は損害として認められます。修理費は修理をしたことを損害とするのではなく、損傷による原状回復の費用が損害と考えられるからです。
例えば、協定で100万円の修理費として認められた場合、100万円を受け取って、実際には修理しないで車を廃車にするということも可能です。
評価損も請求できる場合がある
修理可能な場合でも、事故により車両の市場価値が下がることがあります。これを「評価損」といい、一定の条件下で損害として認められます。
評価損が認められやすいのは:
- 新車登録から3年以内、走行距離3万km未満の車両
- 骨格部分(フレーム等)に損傷がある場合
- 高級車や外国車での事故
認定された評価損の金額は、通常、修理費の10〜30%程度が一つの目安です。
まとめ – 納得できない時価額には適切に対応を

交通事故で提示された時価額に納得できない場合、泣き寝入りする必要はありません。適切な対応により、正当な補償を受けられる可能性があります。
重要なポイント:
- 時価額の算定根拠を明確に確認する
- 中古車市場の実態を示す資料を収集する
- 買替諸費用も含めて請求する
- 交渉が難航したら早めに弁護士に相談する
- 弁護士特約があれば積極的に活用する
物損事故は、意外と保険会社と争いになることがあります。物損と一緒に怪我をしている場合は、慰謝料や後遺障害でも争いになる可能性があります。
時価額の問題で悩んでいる方、保険会社の対応に納得できない方は、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談することをお勧めします。
ご相談・ご質問

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。
LINEでの相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。