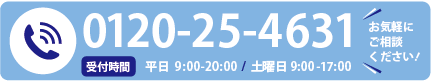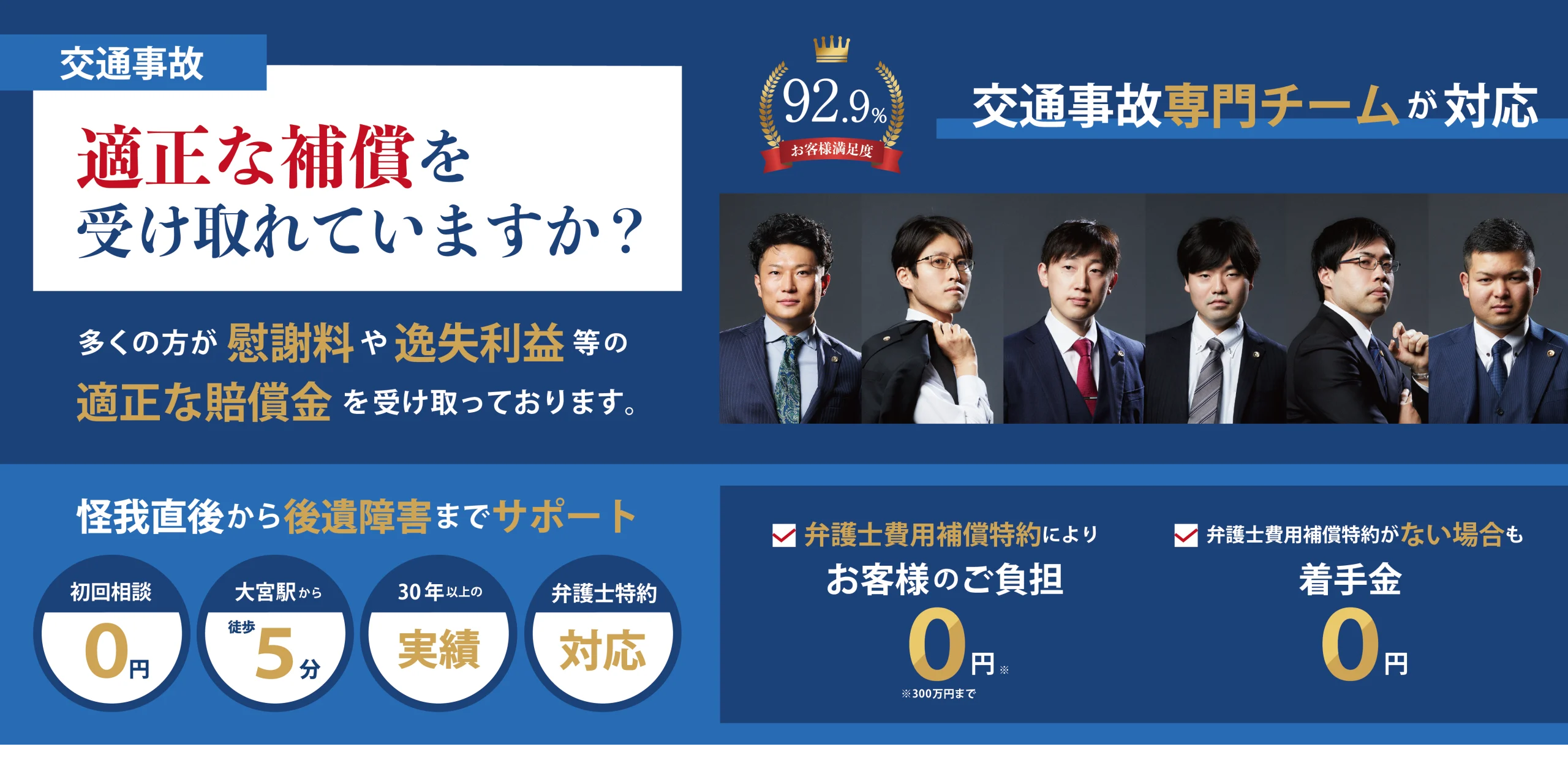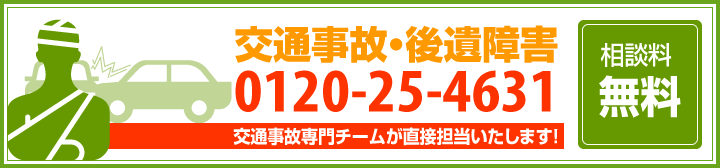埼玉の法律事務所であるグリーンリーフ法律事務所が、「ライプニッツ係数」についてわかりやすく解説します。
ライプニッツ係数とはなんですか?

やや難しい概念ですので簡単に言いますと、「将来にわたる損害金を一度に受け取るのだから、利息を引きましょう」という考え方です。
逸失利益の請求は、長期間にわたって発生する収入減少による損害を、一時金で受け取ります。したがって、将来の利息分(中間利息)を差し引いて計算することになります。
すなわち、一度に受け取ったお金を運用すれば、利息が増えるのだから、現在請求できる金額は、将来もらえるはずの金額からそれまでの利息分を控除した金額となります。
中間利息控除は、事故日によって変わります。以前は年5%が前提とされていましたが、民法が改正されたことにより、2020年4月1日以降の事故については、年3%となりました。
ライプニッツ係数を使った計算例

架空の例をあげると、一家の大黒柱(40歳)が交通事故で高次脳機能障害などになり寝たきりになってしまったとします。
その場合、
・年収500万円
・労働能力喪失率100%(寝たきりなので年収が0になるという意味)
・40歳~67歳まで働けるとして、27年
そうすると、500万×100%×27年=1億3500万円という計算がでます。
しかし、交通事故の実務は、以下のように計算します。
・年収500万円
・労働能力喪失率100%(寝たきりなので年収が0になるという意味)
・40歳~67歳まで働けるとして、27年→ライプニッツ係数18.3270(2020年4月1日以降の事故)若しくは14.643(2020年4月1日以前の事故)
そうすると、500万×100%×18.327年=9163万5000円
ライプニッツ係数を使わない場合と比べて、4500万円程度少なくなってしまいました。
ライプニッツ係数の問題点

実は、ライプニッツ係数をつかう計算には大きな問題が含まれています。
現在の経済状況で、年3%(若しくは5%)も利息を増やす手段は、非常に限られたものになっています。定期預金にあずけても、全く利息はつきません。
それにもかかわらず、3%が基準となっているのです(民法における定めが影響しているので、現在の実務でこの点を争うのは困難です)。
中間利息控除の計算方法には、複利計算方式のライプニッツ方式と、単利計算方式のホフマン係数があり、どちらをとるかにより数字が変わってきます。
ですが、東京・大阪・名古屋の裁判所の計算方法は、原則として、ライプニッツ方式での計算をすることになっています。
以下、参考として、ライプニッツ係数の表を載せておきます。
ライプニッツ係数表
こちらのライプニッツ係数一覧表にまとめました。
(別ページに飛びます)
まとめ
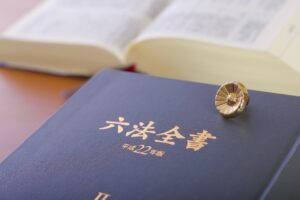
交通事故に遭って後遺障害が残ったケースや、死亡事故のケースでは逸失利益が損害として発生します。
その際、逸失利益の計算にライプニッツ係数を使用することになります。
計算がよくわからない、損害額が相場と比べて適切かわからないという場合は弁護士にご相談ください。
交通事故に強い法律事務所に相談