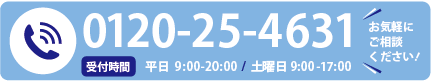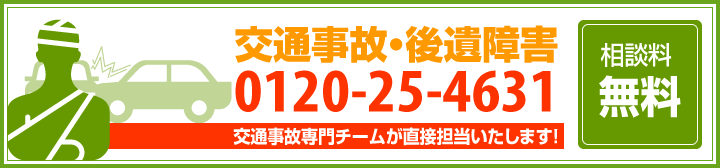紛争の内容(ご相談前の状況)
依頼者は、ご子息を助手席に乗せ、幹線道路を自動車で走行していたGさん(40代・男性)。
その日の夕方、Gさんが青信号の交差点を直進中、道路脇の駐車場から安全確認をしないまま、一台の車が突然飛び出してきました。
Gさんは急ブレーキをかけましたが間に合わず、相手の車と衝突。この事故で、Gさんと同乗していた息子さんは、共に首や腰を捻挫するなどの怪我を負われました。
事故後、相手方の保険会社担当者と交渉を開始しましたが、早々に大きな問題が浮上します。それは「過失割合」でした。
保険会社は、「Gさんの車も動いていた以上、Gさんにも一定の過失がある」として、Gさん側に不利な過失割合を提示。Gさんは、ルールを守って走行していたにもかかわらず、大きな責任を問われることに到底納得できませんでした。また、お二人とも痛みが長引き、通院が長期化する見込みで、今後の補償についても大きな不安を抱えていました。
「このままでは、正当な補償を受けられないかもしれない」
そう考えたGさんは、交通事故の専門家である当事務所にご相談に来られました。
交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
ご依頼を受けた弁護士は、まずGさんと息子さんのお怪我の治療に専念していただく環境を整えました。その上で、事故状況を詳細に分析し、相手方保険会社との本格的な交渉に臨みました。
本件最大の争点は「過失割合」です。弁護士は、過去の膨大な交通事故裁判例を類型化した専門書籍『判例タイムズ』に基づき、本件事故の基本的な過失割合を算出。
その上で、ドライブレコーダーの映像を精査し、本来は20:80であることを確認しつつ、幹線道路の割合ー5を適用し、15:85となりました。
並行して、約8ヶ月弱に及んだ通院についても、治療の必要性を医学的見地から主張。痛みが長引いたことによる精神的苦痛に対する慰謝料は、当然に「裁判基準(弁護士基準)」で支払われるべきであると、一貫して求め続けました。
本事例の結末(結果)
弁護士による専門的な交渉の結果、当初保険会社が提示していた過失割合(20:80)は覆り、最終的に【Gさん側:15% 対 相手方側:85%】という過失割合で合意に至りました。
慰謝料についても当方の主張が全面的に認められ、裁判基準満額で算定されました。
最終的に、ご自身の過失分(15%)が差し引かれた後でも、Gさん・息子さんそれぞれが、治療費込みで約100万円の損害賠償金を受け取ることができ、納得のいく形で解決を迎えられました。
本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
交通事故において、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも絶対的なものではありません。
事故の具体的な状況(場所、時間、相手の運転態様など)によって、過失割合は大きく変動します。
保険会社の担当者は、自社にとって有利な過失割合を主張してくることが少なくありません。
それに納得できないまま示談してしまうと、受け取れる賠償金が大幅に減額されてしまう恐れがあります。
弁護士は、『判例タイムズ』のような専門的知見や過去の裁判例に基づき、依頼者様にとって最も有利な過失割合を主張・立証することが可能です。
「自分の車も動いていたから仕方ない」と諦める必要はありません。
相手方から提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、示談書(免責証書)にサイン(もしくは口頭で承諾)をする前に、ぜひ一度、交通事故の専門家にご相談ください。