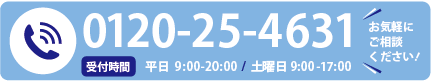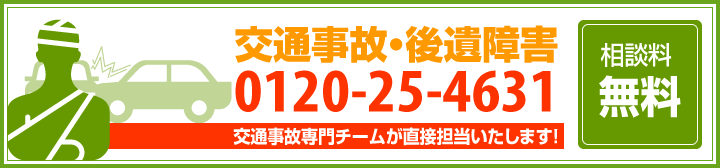紛争の内容
依頼者(被害者)は、自動車を運転中、追突事故に遭い、むちうち(頚椎捻挫)の傷害を負いました。
相手方(加害者)は任意保険に加入していましたが、依頼者は早期の治療費や休業損害の補填のため、ご自身が加入する人身傷害保険から、先に一部の賠償金(治療費、休業損害、慰謝料等)の支払いを受けていました。
症状固定後、後遺障害等級は非該当となりましたが、人身傷害保険で既に支払いを受けた金額と、本来、裁判所が認める基準(裁判基準)で算定される賠償金との間に大きな差額が生じると判明しました。
この差額(主に慰謝料や逸失利益の部分)を、加害者側の任意保険会社に対して請求するための交渉・手続きをご依頼いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任・裁判基準での損害額算定: まず、弁護士が介入し、改めて依頼者の損害(治療期間、傷害の程度、休業状況等)を精査し、裁判基準(弁護士基準)に基づいた適正な賠償額を算定しました。
人身傷害保険から既に受領した金額は、この総額から控除する形となります。
保険会社との交渉開始: 加害者側の任意保険会社に対し、裁判基準で算定した損害額と、人身傷害保険の支払い額との差額の支払いを求める請求書を送付し、交渉を開始しました。当初、保険会社は、既払い金との関係や、後遺障害がないことを理由に、裁判基準での満額の支払いに難色を示しました。
粘り強い交渉と法的論拠の提示: 弁護士は、過去の裁判例や類似事案における判例を踏まえ、むちうちの傷害であっても通院期間や頻度から適正な傷害慰謝料が認められるべきであること、また、人身傷害保険の支払いは、加害者側の賠償義務を完全に免除するものではないことなどを、法的論拠をもって粘り強く主張しました。
示談による解決: 複数回の交渉の結果、保険会社は当方の主張の正当性を認め、最終的に、当初の提示額を大きく上回る金額(裁判基準で算定された総損害額から人身傷害保険既払い分を差し引いた差額の大部分)で和解するに至りました。
本事例の結末
依頼者は、人身傷害保険から先行して支払いを受けていたにもかかわらず、弁護士による交渉の結果、最終的な賠償総額が裁判基準に近い水準となり、経済的な不利益を受けることなく、適正な賠償金として差額分を相手方保険会社から受け取ることができました。
本事例に学ぶこと
人身傷害保険の活用と限界: 交通事故において、ご自身の人身傷害保険を利用することで、早期に治療費や当面の生活費を確保できるメリットがあります。
しかし、この保険の支払基準は、一般的に裁判所が認める基準(裁判基準)より低く設定されていることが多いため、その差額については、別途、加害者側に対して請求することが可能です。
「裁判基準差額」の重要性: 既に人身傷害保険から支払いを受けている場合でも、弁護士が介入し「裁判基準」で損害額を算定し直すことで、数百万円単位の賠償金が増額する可能性があります。
「人身傷害で終わり」と諦めず、適正な賠償額を追求することが重要です。
弁護士介入のタイミング: 人身傷害保険からの支払いを受けた後であっても、弁護士にご相談いただくことで、損害賠償請求権の時効に注意しながら、裁判基準による差額請求を適切に進めることができます。
特に、後遺障害が非該当とされた事案でも、弁護士基準で算定する傷害慰謝料は増額することがあります。